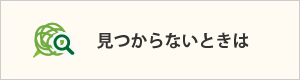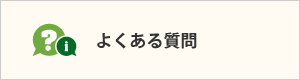国民健康保険税
国民健康保険税(以下「国保税」といいます。)は,大郷町の国民健康保険(以下「国保」といいます。)に加入されている被保険者の医療費等をまかなうための保険料としてかかる税金です。被保険者の皆さんが病気やけがをした時,心配なく医療を受けるための貴重な財源となっています。
下記のお知りになりたい項目をクリックしてご覧ください。
国保税の納税義務者
国保税は世帯の世帯主に課税されます。
国保は勤務先の健康保険と異なり,加入者自身に収入がない場合が多いこともあり,納税義務者はその世帯の主たる生計維持者である世帯主とされています。
世帯主が国保の被保険者でない場合(他の健康保険に加されている場合)でも,その世帯内に国保の被保険者がいる場合には,その世帯主が納税義務を負うこととなります。このような世帯主を「擬制世帯主」といいます。
国保税の税率について
国保税は、医療分、後期高齢者支援金分(支援分)、介護分の3つの区分に分かれており、その合計額が年額(4月から翌年3月までの分)になります。
なお、年度の途中で国保の資格異動(出生、死亡、転入、転出、社会保険等加入・離脱等)があった場合は、国保への加入期間に応じて、月割りで計算します。
※計算式は下記計算例を参照
令和7年度以降の税率及び限度額は次のとおりです。
|
区分 |
加入者全員が課税されます |
40歳以上65歳未満 |
|
|
(1)医療分 |
(2)後期高齢者支援分 |
(3)介護納付金分 |
|
|
※1所得割 |
6,2% |
2,2% |
2,0% |
|
均等割 |
23,000円 |
8,500円 |
9,300円 |
|
平等割 |
17,000円 |
6,000円 |
4,700円 |
|
賦課限度額 |
660,000円 |
260,000円 |
170,000円 |
※1 所得割は、加入者の前年(1月から12月)の所得により算定します。その際、加入者それぞれの所得から基礎控除として43万円が控除されます。
〇計算例
例 :世帯主(43歳)営業所得2,000,000円
妻(35歳) 給与収入1,200,000円(給与所得650,000円)
子ども(10歳)中学生
1.医療分の計算
(1)所得割
世帯主(2,000,000円-430,000円)×6,2%=97,340円
妻 (650,000円-430,000円)×6,2%=13,640円
(2)均等割
23,000円×3人=69,000円
(3)平等割
1世帯あたりの額=17000円
合計額 (1)+(2)+(3)=196,980円…(A)
2.支援分の計算
(1)所得割
世帯主(2,000,000円-430,000円)×2,2%=34,540円
妻 (650,000円-430,000円)×2,2%=4,840円
(2)均等割
8,500円×3人=25,500円
(3)平等割
1世帯あたりの額=6,000円
合計額 (1)+(2)+(3)=70,880円…(B)
3.介護分の計算(40歳~64歳の方が対象)
(1)所得割
世帯主(2,000,000円-430,000円)×2,00%=31,400円
(2)均等割
9,300円×1人=9,300円
(3)平等割
1世帯あたりの額=4,700円
合計額 (1)+(2)+(3)=45,400円…(C)
国保税年額{(A)医療分+(B)支援分+(C)介護分}
196,980円+70,888円+45,400円=313,260円
100円未満切捨てにより年税額⇒ 313,200円
国保税の軽減制度
〇低所得世帯に対する軽減(申請不要)
所得の低い世帯の負担を少なくするために、世帯主及び被保険者の前年中の所得金額の合計が以下の基準に該当する場合、国保税の均等割と平等割について、軽減割合(7割、5割、2割)に応じ減額し計算します。
軽減判定
|
軽減 割合 |
軽減判定基準額 |
|
7割 |
43万円+{10万円×(給与所得者等(注1)の数-1)}以下 |
|
5割 |
43万円+(30万5千円×被保険者数)+{10万円×(給与所得者等(注1)の数-1)}以下 |
|
2割 |
43万円+(56万円×被保険者数)+{10万円×(給与所得者等(注1)の数-1)}以下 |
(注1)給与所得(給与収入55万円超)を有する方、公的年金等に係る所得(公的年金の収入60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上))を有する方、または、その両方を有する方。
注意事項
- 申請は不要ですが、前年の所得金額を申告していない世帯主や国保加入者がいる世帯は判定が保留になってしまい、軽減を受けることができません。
- 軽減判定所得は、以下のものは保険税の算定とは異なる方法により算出します。
・1月1日時点で65歳以上の公的年金受給者は、年金所得から15万円を差し引いた額が軽減判定所得となります。なお、年金所得が15万円未満の場合は、その全額が控除額となります。
・事業専従者控除がある方は、控除前の額が軽減判定所得となります。
・専従者給与がある方は、軽減判定所得には含みません。
・土地・建物等の分離課税の長期譲渡所得は、特別控除前の額が軽減判定の所得となります。
・雑損失の繰越控除がある方は、控除後の額が軽減判定所得となります。
〇未就学児均等割軽減(申請不要)
子育て世帯への経済的負担の軽減の観点から、多子世帯や低所得世帯による制限をかけず、広く未就学児がいる世帯に対して、一律に未就学児の均等割額の2分の1を減額します。
既に、低所得者の均等割軽減が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額の2分の1を減額します。
|
低所得者の均等割 軽減割合 |
(低所得者軽減措置後)―(未就学児減額分)=(減額後の額) |
|
7割軽減 |
9,450円 - 4,725円 = 4,725円 |
|
5割軽減 |
15,750円 - 7,875円 = 7,875円 |
|
2割軽減 |
25,200円 - 12,600円 =12,600円 |
|
軽減なし |
31,500円 - 15,750円 =15,750円 |
※表中の税額は、医療費給付費分と後期高齢者支援金等分の均等割合計額です。
※未就学児(満6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)が対象
※未就学児が2人以上加入している場合や所得割額によっては100円未満の端数調整が生じますので、未就学児1人あたりの均等割額が必ずしもこの金額とは限りません。
〇非自発的失業者に対する軽減(申請必要)
倒産、解雇、雇い止めなどの理由で離職された方が、在職中と同程度の保険料負担で医療保険に加入することができるよう、国保税の計算の基礎となっている前年の所得のうち、離職者本人の給与所得を100分の30とみなして計算します。
◎対象者
次のすべてに該当する方です。
- 離職時65歳未満の方
- ハローワークで発行される雇用保険受給資格者証に記載されている離職理由コードが〔11、12、21、22、23、31、32、33、34〕の方
◎軽減期間
離職日の翌日から翌年度末までの期間です。
〇国保から後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減(申請不要)
後期高齢者医療制度への移行が生じたことにより、国保加入者が1人だけとなる世帯について、医療分と支援分の平等割額が減額になります。緩和措置期間は8年間で、最初の5年間は2分の1、続く3年間は4分の1が減額されます。ただし、期間中に他の世帯員の方が国民健康保険に加入した場合は終了します。
〇社会保険等の被扶養者であった方(旧被扶養者)にかかる減免(申請必要)
被用者保険(会社の健康保険など)から後期高齢者医療制度に移行することにより、被用者保険の被扶養者から国保被扶養者となった65歳以上の方(旧被扶養者)については、申請することで次のような減免が受けられます。
・旧被扶養者に係る所得割額を当分の間全額免除します
・旧被扶養者に係る医療分と支援分の均等割額を資格取得後2年間半額にします(7割及び5割軽減世帯に該当の場合は除く)
・旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、平等割を資格取得後2年間半額にします(7割及び5割軽減世帯に該当の場合は除く)
○産前産後期間における軽減(申請必要)
子育て世帯の負担軽減、次世代育成の観点から、出産する国民健康保険被保険者に係る産前産後期間相当分の国保税所得割、均等割が軽減されます。
※詳しい制度の内容はこちらをご覧ください。
→令和6年1月から国民健康保険税の産前産後軽減制度が始まります(大郷町ホームページ)
国保税の減免
国保税の減額を受けられない方で,天災・生活困窮・刑務所等の施設に収容されている場合やその他の特別な事情により保険税を納めることが困難なときは,減免が認められる場合もあります。
また、事情により納付が困難な場合には、納期限前に税務課特別徴収係へご相談ください。
月割課税
年度の途中で加入した方の国保税は、加入の届出をした月にかかわらず、国保に加入する資格を取得した月から月割計算します。
また、年度の途中で国保の資格を喪失した方は、国保の資格を喪失した月の前月までの分を月割計算します。
(例)
9月に国保に加入した場合
9月から3月までの7ヶ月分を課税します。(年間の国保税×12分の7)
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|
9月に国保を離脱した場合
4月から8月までの5ヶ月分を課税します。(年間の国保税×12分の5)
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|
国保税の納期
自主納付(普通徴収)で納めていただく方の納期は、次の10期です。
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | ||
| 暫定賦課 | 本算定賦課 | ||||||||||
※本算定賦課において、前年中の所得が確定したことにより年間の国保税額が決定します。暫定賦課の対象となった世帯は、暫定賦課分を差し引いた金額を第3期から第10期で納付していただきます。なお、暫定賦課で納めた額が本算定賦課額を上回った場合は、原則として還付されます。
国保税の特別徴収(年金天引き)
次の2つの要件を満たす場合には、世帯主の年金から国保税が特別徴収(天引き)されます。
対象者
- 世帯主が国保に加入している場合で、世帯の国保加入者全員が65歳から74歳の場合
- 世帯主の受給されている年金が、年額18万円以上で、介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金受給額の2分の1を超えない場合
- 介護保険料が年金特徴されている
よくある質問Q&A
Q1:国保税は誰が納めるのですか?
A1:住民票上の世帯主に納めていただくことになります。
国保税は、世帯主に課税することが地方税法及び条例で定められています。そのため、世帯主が他の健康保険(社会保険や後期高齢者医療制度)に加入している場合でも、納税通知書は世帯主あてに送付します。
Q2:社会保険等の任継続保険料と国保税ではどちらが安いですか?
A2:社会保険等の任意継続保険料と国保税の算定の基になる金額や税率はそれぞれ違うため一概にどちらが安いということは言えません。
なお、国保税の税額はおおよその額を試算できますので、税務課までお問い合わせ下さい。社会保険等は自身が加入している社会保険事業所にお問い合わせのうえ、比較検討してください。
Q3:月の初めに国民健康保険から脱退する手続きをしたのですが、その月の国保税は納めなくてよいですか?
A3:納付をしてください。
国保税は社会保険と違い、毎月払いではなく1年分(4月から翌年3月の12ヶ月分)を10回の納期に分けて納付するものです。つまり、各納期の税額はその月分の国保税とはならず、月割りで算定した結果、喪失の月以降にも納めていただくべき国保税額が残ることがありますので、納付をお願いします。
国保税の算定のやり直しは、脱退手続きのあった月の月末に行い、お手続きいただいた翌月15日頃に更正決定通知を発送します。
なお、算定のやり直しによって、納めすぎが生じた場合、滞納がなければ還付いたします。
Q4:社会保険に加入したのに納税通知書が届くのはなぜですか?
A4:国保税の納税義務者は世帯主です。世帯主が国保に加入していなくても、同世帯の者が国保に加入している場合、世帯主の方宛に納税通知書を発送しています。
または国保の脱退手続きを行っていない可能性があります。脱退手続きをしていない場合は、速やかに町民課にて手続きをしてください。
Q5:他の市区町村に転出したら、両方の市区町村から国保税の納税通知書が届きました。どちらの税金を納めたほうがいいですか?
A5:他の市区町村へ転出した後に届く大郷町の納税通知書は、転出により国保税の加入月数が変更されたため、再計算されたものです。したがって納付がある場合は納期限通りに納付してください。
例えば、9月10日で大郷町から転出した場合、大郷町での加入月数分(4月~8月)で再計算したものを送付します。そして転出先の市区町村で加入月分(9月~3月)について計算されたものが通知されます。
Q6:なぜ4月と7月の2回に分けて納付書が届くのですか?
A6:暫定賦課と本算定賦課があるためです。
〇暫定賦課
国保税の普通徴収分(納付書または口座振替による納付)を1期~10期の10回で納めていただいております。税額は前年中の所得などにより決定しますが、所得の把握が6月までかかるため、4月・5月・6月分までは仮計算により算出した暫定賦課額を納めていただきます。暫定賦課額分の納税通知書は毎年4月中旬に送付しています。
〇本算定
本算定とは、確定した所得金額をもとに国保税額を計算することです。
6月に確定した前年の所得金額を基に年間の国保税額を計算します。そこから、4月・5月・6月の仮算定分を差し引いた残りの金額を7月から納めます。
本算定の納税通知書は毎年7月中旬に送付しています。
Q7:会社を退職して収入が無いのにも関わらず国保税が高いのはなぜですか?
A7:前年中(1月~12月)までの所得をもとに計算しているためです。
加入時現在で収入がない方でも、国保税は地方税法により課税すべき年度分の前年中(1月~12月)までの所得をもとに計算するので、前年中の所得が多いと国保税は高くなります。
なお、納付が難しい場合は一度税務課特別徴収係へご相談ください。